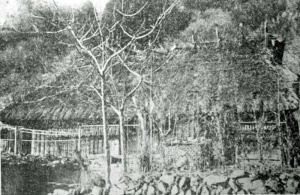|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
普寛旧跡
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2018年5月28日 (月)
(版間での差分)
| (間の15版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| + | {|class="wikitable" style="width:800px;margin:0 auto;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;background-color:#ededed"|'''普寛旧跡''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *[[目次#日本編|日本編]] >> [[目次#神道|神道]] >> [[目次#信仰系譜|信仰系譜]] >> [[木曽御嶽信仰]] >> [[普寛旧跡]] | ||
| + | *[[目次#日本編|日本編]] >> [[目次#修験道|修験道]] >> [[目次#霊場・信仰系譜|霊場・信仰系譜]] >> [[木曽御嶽信仰]] >> [[普寛旧跡]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| | ||
| + | [[ファイル:ontake_fukan-jinja_006.jpg|300px]] | ||
| + | [[ファイル:ontake C008 講祖本社04.jpg|300px]]<br> | ||
| + | 左:普寛の生家(現存せず) 右:普寛百年祭碑 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="36.438961" lon="138.795776" type="map" zoom="8" width="800" height="500" controls="large"> | ||
| + | http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&vps=1&jsv=327b&brcurrent=h3,0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244&msa=0&output=nl&msid=208806612508013451037.0004a7dfaa6ee49ea5dc0 | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==概要== | ||
| + | '''普寛'''(ふかん)(1731-1801)は、[[覚明]]とともに[[木曽御嶽山]]を開き、[[木曽御嶽信仰]]の開祖となった[[天台宗]][[修験]][[修験道の諸師旧跡|僧]]。木曽御嶽信仰独自の憑霊儀礼である'''御座'''(おざ)は普寛が[[不動明王]]から授けられたものとされる。武蔵秩父出身。'''普寛行者'''、'''普寛霊神'''。 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="float:right;width:100px;background-color:#66ccff;" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <amazon>4872945697</amazon> | ||
| + | 登山の前に。手頃なガイドブック | ||
| + | | | ||
| + | <amazon>487294254X</amazon> | ||
| + | 信仰の世界へ。宗教人類学的研究 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==旧跡== | ||
| + | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 17行: | 52行: | ||
|三峰山で日照のもとにいたころ、両神山の金剛院でも修行していたという伝承がある。金剛院ではのちの弟子の順明の祖父に師事したという。(『木曽御嶽信仰』164) | |三峰山で日照のもとにいたころ、両神山の金剛院でも修行していたという伝承がある。金剛院ではのちの弟子の順明の祖父に師事したという。(『木曽御嶽信仰』164) | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |八丁堀 [[法性院]](廃絶) |
|(江戸八丁堀) | |(江戸八丁堀) | ||
|普寛が住した寺院。下記参照。 | |普寛が住した寺院。下記参照。 | ||
| 41行: | 76行: | ||
|1795年(寛政7年)7月2日に武尊山登頂。『武尊山開闢縁記』および『武尊山開闢記』が伝存している。(『修験と神道のあいだ』304) | |1795年(寛政7年)7月2日に武尊山登頂。『武尊山開闢縁記』および『武尊山開闢記』が伝存している。(『修験と神道のあいだ』304) | ||
|- | |- | ||
| - | |本庄 [[安養院]] | + | |本庄 [[安養院 (埼玉県本庄市)|安養院]] |
| - | | | + | |埼玉県本庄市中央3-3-6 |
|1801年(享和1年)死去。安養院の文龍により葬儀が行われる。安養院に埋葬された。のち、普寛の墓域は普寛霊場として独立する。 | |1801年(享和1年)死去。安養院の文龍により葬儀が行われる。安養院に埋葬された。のち、普寛の墓域は普寛霊場として独立する。 | ||
|- | |- | ||
| - | |本庄 [[普寛霊場]] | + | |本庄 [[本庄普寛霊場|普寛霊場]] |
|埼玉県本庄市中央3-4 | |埼玉県本庄市中央3-4 | ||
| - | | | + | |普寛の墓所四箇所の一つ。遺骨を砕いて、木像に黒漆で塗り固められた「御霊像」が、御堂にご神体として祀られている。 |
|- | |- | ||
|花戸 [[花戸普寛堂|普寛堂]] | |花戸 [[花戸普寛堂|普寛堂]] | ||
| 57行: | 92行: | ||
|普寛の墓所四箇所の一つ。普寛の生誕地。子孫の木村家が代々継承している。創建年代は不明。当初は普寛堂といった。1921年(大正10年)、東京永山教会の寄進により再建。一時期は御嶽教に関わっていたらしい。1944年(昭和19年)2月、火災により焼失。1966年(昭和41年)5月3日、普寛神社として再建。1975年(昭和50年)宗教法人となる。1988年(昭和63年)に神楽殿建設。埼玉県旧跡「普寛行者生地」に指定されている。(以上、「神楽殿建設記念碑」、墓碑より) | |普寛の墓所四箇所の一つ。普寛の生誕地。子孫の木村家が代々継承している。創建年代は不明。当初は普寛堂といった。1921年(大正10年)、東京永山教会の寄進により再建。一時期は御嶽教に関わっていたらしい。1944年(昭和19年)2月、火災により焼失。1966年(昭和41年)5月3日、普寛神社として再建。1975年(昭和50年)宗教法人となる。1988年(昭和63年)に神楽殿建設。埼玉県旧跡「普寛行者生地」に指定されている。(以上、「神楽殿建設記念碑」、墓碑より) | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |八丁堀 [[法性院]](廃絶) |
|(江戸八丁堀) | |(江戸八丁堀) | ||
|普寛が住した寺院。本山派修験寺院。1766年(明和3年)、普寛は権大僧都となり、本明院と称して、法性院に住した。これは叔父の伯忍の跡を継いだものだという(菅原寿清「覚明・普寛とその弟子達の時代」)。普寛の墓所四箇所の一つ。廃絶。御嶽山大教普寛大殿教会に遺骨が一部伝存しているという(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 | |普寛が住した寺院。本山派修験寺院。1766年(明和3年)、普寛は権大僧都となり、本明院と称して、法性院に住した。これは叔父の伯忍の跡を継いだものだという(菅原寿清「覚明・普寛とその弟子達の時代」)。普寛の墓所四箇所の一つ。廃絶。御嶽山大教普寛大殿教会に遺骨が一部伝存しているという(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |新宿 御嶽山大教[[普寛大殿教会]] |
|東京都新宿区新宿5丁目2 | |東京都新宿区新宿5丁目2 | ||
|普寛の墓所四箇所の一つ。法性院のものの一部が伝存している(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 | |普寛の墓所四箇所の一つ。法性院のものの一部が伝存している(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 | ||
|- | |- | ||
| - | |金剛院御嶽神社 | + | |両神山 [[金剛院御嶽神社]] |
| - | | | + | |埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄6785 |
|普寛の分骨があるという。(椿真智子・城戸貴子 1991「秩父両神村における修験の展開と変質」104) | |普寛の分骨があるという。(椿真智子・城戸貴子 1991「秩父両神村における修験の展開と変質」104) | ||
|- | |- | ||
| - | |[[法称寺]] | + | |武尊山 [[法称寺]] |
| - | | | + | |群馬県利根郡片品村花咲 |
| - | | | + | |普寛分骨が伝存している。 |
|- | |- | ||
| - | | | + | |高崎 [[高崎普寛堂|普寛堂]] |
|群馬県高崎市貝沢町322 | |群馬県高崎市貝沢町322 | ||
| - | | | + | |高崎にある御嶽講の普寛堂。伝承によると、普寛の分骨を納めているという。五霊神社に接する。 |
|- | |- | ||
| - | | | + | |王滝 [[王滝普寛堂|普寛堂]] |
|長野県木曽郡王滝村 | |長野県木曽郡王滝村 | ||
| - | | | + | |王滝にある普寛堂 |
|- | |- | ||
| - | | | + | |王滝 [[王滝講祖本社|講祖本社]] |
|長野県木曽郡王滝村 | |長野県木曽郡王滝村 | ||
| - | | | + | |王滝にある御嶽行者を合祀した堂 |
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| 98行: | 131行: | ||
ファイル:Iharayama 02.jpg|意波羅山三社宮 | ファイル:Iharayama 02.jpg|意波羅山三社宮 | ||
ファイル:Iharayama 03.jpg|意波羅山三社宮 | ファイル:Iharayama 03.jpg|意波羅山三社宮 | ||
| + | ファイル:ontake C008 講祖本社01.jpg|王滝 講祖本社 普寛の木像と銅像が祀られている | ||
| + | ファイル:ontake C008 講祖本社02.jpg|王滝 講祖本社 | ||
ファイル:ontake C008 講祖本社04.jpg|王滝 講祖本社 普寛百年祭碑 | ファイル:ontake C008 講祖本社04.jpg|王滝 講祖本社 普寛百年祭碑 | ||
ファイル:ontake C007 普寛堂01.jpg|王滝普寛堂 | ファイル:ontake C007 普寛堂01.jpg|王滝普寛堂 | ||
ファイル:ontake C007 普寛堂02.jpg|王滝普寛堂 | ファイル:ontake C007 普寛堂02.jpg|王滝普寛堂 | ||
| + | ファイル:Ontake_C003_王滝御嶽神社_里宮12.jpg|王滝里宮にある普寛供養碑(最古の普寛の碑?) | ||
| + | ファイル:ontake_fukan-jinja_006.jpg|普寛の生家(現存せず) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[category:人物旧跡]] | ||
2018年5月28日 (月) 時点における最新版
| 普寛旧跡 |
概要
普寛(ふかん)(1731-1801)は、覚明とともに木曽御嶽山を開き、木曽御嶽信仰の開祖となった天台宗修験僧。木曽御嶽信仰独自の憑霊儀礼である御座(おざ)は普寛が不動明王から授けられたものとされる。武蔵秩父出身。普寛行者、普寛霊神。
|
登山の前に。手頃なガイドブック |
信仰の世界へ。宗教人類学的研究 |
旧跡
| 名称 | 所在地 | コメント |
|---|---|---|
| 秩父 普寛神社 | 埼玉県秩父市大滝944 | 普寛の生誕地。生家跡。下記参照。 |
| 秩父 三峰山高雲寺観音院(三峰神社) | 埼玉県秩父市三峰298-1 | 普寛が出家した寺院。江戸で酒井神楽頭家に仕えていた普寛(木村好八)は思うところがあって、1764年(明和1年)に三峰山高雲寺観音院(三峰神社)にて出家した。観音院は本山派二十七先達の一つ。普寛は日照に師事して、本山派修験者となった。 |
| 両神山 | 埼玉県秩父市、秩父郡小鹿野町 | 三峰山で日照のもとにいたころ、両神山の金剛院でも修行していたという伝承がある。金剛院ではのちの弟子の順明の祖父に師事したという。(『木曽御嶽信仰』164) |
| 八丁堀 法性院(廃絶) | (江戸八丁堀) | 普寛が住した寺院。下記参照。 |
| 上野 三笠山 | 群馬県多野郡上野村 | 1790年(寛政2年)に普寛が三笠山を開いたという。(『木曽御嶽信仰』211) |
| 秩父 意波羅山 | 埼玉県秩父市 | 1792年(寛政4年)2月、三社宮を創建。『普寛行者道中日誌』による。(『修験と神道のあいだ』263)。 |
| 木曽 御嶽山 | 長野県木曽郡木曽町・王滝村 | 1792年(寛政4年)6月8日に初登拝。6月10日に頂上に到達。翌1793年(寛政5年)6月13日に二回目の登拝。さらに翌1794年(寛政6年)6月1日に三回目の登拝。『普寛行者道中日誌』による。(『修験と神道のあいだ』24) |
| 越後 八海山 | 新潟県南魚沼市 | 普明の『八海山開闢伝紀』によると、1794年(寛政6年)6月18日に登拝して屏風本社を祀ったとされる(鈴木昭英2004:31)。しかし、このとき普寛は木曽御嶽山に滞在していたはずなので、このまま史実だとはいえないようである。 |
| 上野 武尊山 | 群馬県利根郡みなかみ町、川場村、片品村 | 1795年(寛政7年)7月2日に武尊山登頂。『武尊山開闢縁記』および『武尊山開闢記』が伝存している。(『修験と神道のあいだ』304) |
| 本庄 安養院 | 埼玉県本庄市中央3-3-6 | 1801年(享和1年)死去。安養院の文龍により葬儀が行われる。安養院に埋葬された。のち、普寛の墓域は普寛霊場として独立する。 |
| 本庄 普寛霊場 | 埼玉県本庄市中央3-4 | 普寛の墓所四箇所の一つ。遺骨を砕いて、木像に黒漆で塗り固められた「御霊像」が、御堂にご神体として祀られている。 |
| 花戸 普寛堂 | 長野県木曽郡王滝村 花戸 | 普寛の墓所四箇所の一つ。普寛の死後、分骨が納められた。吉左衛門(麓講祖、吉神行者)が普寛堂を建立。子孫の小谷家が堂守を務めている(『御嶽の歴史』161)。50年忌の1848年(嘉永1年)6月、江戸高砂講によって、「開闢木食普寛行者」の碑が建立される(『三岳村誌 上巻』823)。広山、順明、泰賢が関わる。『御嶽の歴史』313 |
| 秩父 普寛神社 | 埼玉県秩父市大滝944 | 普寛の墓所四箇所の一つ。普寛の生誕地。子孫の木村家が代々継承している。創建年代は不明。当初は普寛堂といった。1921年(大正10年)、東京永山教会の寄進により再建。一時期は御嶽教に関わっていたらしい。1944年(昭和19年)2月、火災により焼失。1966年(昭和41年)5月3日、普寛神社として再建。1975年(昭和50年)宗教法人となる。1988年(昭和63年)に神楽殿建設。埼玉県旧跡「普寛行者生地」に指定されている。(以上、「神楽殿建設記念碑」、墓碑より) |
| 八丁堀 法性院(廃絶) | (江戸八丁堀) | 普寛が住した寺院。本山派修験寺院。1766年(明和3年)、普寛は権大僧都となり、本明院と称して、法性院に住した。これは叔父の伯忍の跡を継いだものだという(菅原寿清「覚明・普寛とその弟子達の時代」)。普寛の墓所四箇所の一つ。廃絶。御嶽山大教普寛大殿教会に遺骨が一部伝存しているという(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 |
| 新宿 御嶽山大教普寛大殿教会 | 東京都新宿区新宿5丁目2 | 普寛の墓所四箇所の一つ。法性院のものの一部が伝存している(菅原「都市における木曽御嶽信仰」)。 |
| 両神山 金剛院御嶽神社 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄6785 | 普寛の分骨があるという。(椿真智子・城戸貴子 1991「秩父両神村における修験の展開と変質」104) |
| 武尊山 法称寺 | 群馬県利根郡片品村花咲 | 普寛分骨が伝存している。 |
| 高崎 普寛堂 | 群馬県高崎市貝沢町322 | 高崎にある御嶽講の普寛堂。伝承によると、普寛の分骨を納めているという。五霊神社に接する。 |
| 王滝 普寛堂 | 長野県木曽郡王滝村 | 王滝にある普寛堂 |
| 王滝 講祖本社 | 長野県木曽郡王滝村 | 王滝にある御嶽行者を合祀した堂 |