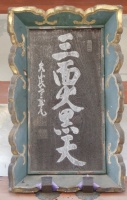|
ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |
東寺
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2024年1月19日 (金)
東寺(とうじ)は、京都府京都市南区にある、空海ゆかりの真言宗の本山寺院。本尊は薬師如来。真言宗の長官である東寺長者を擁し、日本の全真言宗の総本山としての格式を持つ。官寺十五大寺の一つ。西寺と対となる。かつては金剛峰寺も末寺だった。現在は東寺真言宗総本山。伽藍は東院と西院に分かれ、東院に金堂・講堂、西院に御影堂がある。塔頭には本坊、東寺勧学院だった観智院がある。毎年、後七日御修法が行われる灌頂院や平安京羅城門に祀られていた兜拔毘沙門天を継承する毘沙門堂もある。鎮守は伏見稲荷大社で寺の近くに御旅所がある。鎮守には東寺八幡宮、東寺八島社もある。教王護国寺。金光明四天王教王護国寺。左寺。左大寺。普賢総持院。秘密伝法院。山号は八幡山。
目次 |
歴史
伽藍
東院
金堂を中心とする区画
- 金堂:
- 講堂:
- 食堂:
- 五重塔:
- 鐘楼:
- 経蔵:
- 千手堂:
- 護摩堂:
- 護摩壇:屋外にある。
- 灌頂院:後七日御修法が行われている。
- 八幡宮:八幡信仰の神社。
- 八島社:
- 夜叉神堂:
- 弁天堂:弁財天を祀る。
- 善女大龍王:
- 太元堂:大元帥明王を祀る。
- 石上神社:阿刀家執行屋敷の鎮守
- 波切不動尊:阿刀家執行屋敷跡。
西院
空海の住房を起源にするという御影堂を中心とする区画
子院
- 小子房:光厳上皇御所。勅使門がある。本坊が隣接。
- 観智院:本尊は五大虚空蔵菩薩。学頭寺院。金剛蔵聖教を所蔵。
- 宝菩提院:開山は亮禅。亮沢、亮恵、亮兼、禅源らが相続。寺院化した神泉苑を兼務した。
- 光明院:
- 仏乗院:
- 金剛憧院:
- 宝厳院:観智院の東隣にあった。
- 最勝光院:
- 宝輪院:覚王院の東隣にあった。
- 増長院:
- 宝泉院:
- 金蓮院:
- 仏慶院:
- 宝生院:宝勝院?
- 宝光院:
- 正覚院:
- 地蔵院:
- 普賢院:
- 弥勒院:
- 文殊院:
- 薬師院:
- 伝法院:空海(774-835)や藤原三守(785-840)の死後、綜芸種智院を合併する。
- 教令院:開山は長厳。道厳、忠瑜が相続。
- 大悲心院:能禅。
- 金勝院:
- 覚王院:宝厳院の東隣にあった。
- 妙観院:
- 中之坊:
- 奥之坊:
- 真性院:
- 吉祥園院:
関連旧跡
- 伏見稲荷大社御旅所:
- 伏見稲荷大社上御旅所:
- 伏見稲荷大社下御旅所:
- 西寺:
- 綜芸種智院:京都府京都市南区西九条。藤原三守から九条邸を寄進されて開いた。東寺の東隣にあった。現在の近鉄東寺駅のあたりか。
- 長見寺:綜芸種智院跡にあった寺院というが不詳。
- 寛算石:歯神之社
- 戒光寺:東寺の東北にあった。現在は泉涌寺内に移転。
- 浄住寺光明院:東寺学衆の菩提寺だった。
- 神泉苑:
- 真言院
- 念仏寺?
- 鞍馬寺
- 羅城門
組織
造東寺長官ほか
造東寺司は古代の官庁の一つ。
- (造東寺長官)阿倍真勝(754-826):陰陽頭、大学頭、造西寺長官、造東寺長官、神祇伯など歴任。
- (造東寺長官)藤原伊勢人(生没年不詳):796年(延暦15年)造東寺長官就任。同年、鞍馬寺を創建。
- (造東寺次官)多治比家継(生没年不詳):804年(延暦23年)造東寺次官に就任。
- (造東寺別当)勤操(758-827):819年(弘仁10年)、造東寺別当に就任。826年(天長3年)、造西寺別当に転じる。
- (造東寺所別当)長恵:
- (造東寺所別当)空海:824年(天長1年)、造東寺所別当に就任。
東寺長者
東寺長者。明治までは宗派を超えた全真言宗のトップであった。
- 『日本仏家人名辞書』による。
- 未見:「正法務付一長者権法務等補任并諸戒壇院事」:『柳原家記録』所収[1]。
| 世数 | 名 | 生没年 | 就任年 | 略歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空海 | 774-835 | 日本真言宗開祖。 | |
| 2 | 実恵 | 786-847 | 836- | 神護寺別当。786年(延暦5年)生。836年(承和3年)5月10日、東寺長者。847年(承和14年)12月12日死去。 |
| 3 | 真済 | 800-860 | 847- | 神護寺別当。800年(延暦19年)生。847年(承和14年)11月、東寺長者。860年(貞観2年)2月26日死去。 |
| 4 | 真雅 | 801-879 | 861- | 801年(延暦20年)生。861年(貞観3年)、東寺長者。879年(元慶3年)1月3日死去。 |
| 5 | 宗叡 | 809-884 | 879- | 真紹の甥。禅林寺2世。京都・円覚寺開山。809年(大同4年)生。879年(元慶3年)1月、東寺長者。884年(元慶8年)3月26日死去。 |
| 6 | 真然 | 804-891 | 884- | 804年(延暦23年)生。884年(元慶8年)3月、東寺長者。891年(寛平3年)9月11日死去。 |
| 7 | 益信 | 827-906 | 891- | 827年(天長4年)生。891年(寛平3年)9月、東寺長者。906年(延喜6年)3月7日死去。 |
| 8 | 聖宝 | 832-909 | 907-909 | 832年(天長9年)生。907年(延喜7年)3月、東寺長者。909年(延喜9年)6月東寺長者退任。909年(延喜9年)死去。 |
| 9 | 観賢 | 854-925 | 909- | 金剛峰寺座主4世。醍醐寺座主1世。854年(斉衡1年)生。909年(延喜9年)7月、東寺長者。925年(延長3年)6月11日死去。 |
| 10 | 延僘 | 861-928? | 925- | 東大寺別当41世。醍醐寺座主2世。925年(延長3年)6月17日、東寺長者。928年(延長6年)12月13日死去。 |
| 11 | 観宿 | 834-928 | 925- | 東大寺別当40世。貞観寺座主。神護寺別当。金剛峰寺座主5世。925年(延長3年)8月10日、東寺長者。928年(延長6年)12月19日死去。 |
| 12 | 済高 | 870-942 | 928- | 勧修寺長吏。金剛峰寺座主6世。870年(貞観12年)生。928年(延長6年)12月27日、東寺長者。942年(天慶5年)11月25日死去。 |
| 13 | 貞崇 | 866-944 | 942- | 東大寺別当24世。醍醐寺4世。金剛峰寺座主7世。866年(貞観8年)生。942年(天慶5年)11月、東寺長者。944年(天慶7年)7月22日死去。 |
| 14 | 泰舜 | 877-949 | 944- | 金剛峰寺座主8世。877年(元慶1年)生。944年(天慶7年)7月、東寺長者。949年(天暦3年)12月3日死去。 |
| 15 | 寛空 | 884-972 | 949-971 | 大覚寺門跡2世。宇多法皇の弟子。東寺長者15世、仁和寺別当。京都・蓮台寺(香隆寺)を創建。 神護寺別当。金剛峰寺座主9世。884年(元慶8年)生。949年(天暦3年)12月、東寺長者。971年(天禄2年)東寺長者退任。972年(天禄3年)2月6日死去。 |
| 16 | 救世 | 890-973 | 971- | 金剛峰寺座主10世。971年(天禄2年)、東寺長者。973年(天延1年)死去。 |
| 17 | 寛静 | 901-979 | 973- | 金剛峰寺座主11世。901年(延喜1年)生。973年(天延1年)、東寺長者。979年(天元2年)10月11日死去。 |
| 18 | 定照(定昭) | 906-983 | 979-981 | 金剛峰寺座主12世。興福寺一乗院開山。大覚寺3世。興福寺別当。金峰山寺検校。979年(天元2年)10月、東寺長者。981年(天元4年)8月14日、東寺長者退任。983年(永観1年)3月21日死去。 |
| 19 | 寛朝 | 916-998 | 981- | 成田山新勝寺開山。東大寺別当58世。金剛峰寺座主13世。916年(延喜16年)生。981年(天元4年)8月30日、東寺長者。998年(長徳4年)6月14日死去。 |
| 20 | 雅慶 | 926-1012 | 998- | 東大寺別当63世。勧修寺長吏。東寺長者20世。金剛峰寺座主14世。926年(延長4年)生。998年(長徳4年)、東寺長者。1012年(長和1年)10月25日死去。 |
| 21 | 深覚 | 955-1043 | 1012-1013 | 東大寺別当60・62・68世。勧修寺長吏。禅林寺5世。東寺長者21・23・25世。藤原師輔の子。955年(天暦9年)生。1012年(長和1年)、東寺長者。1013年(長和2年)2月日、東寺長者退任。1043年(長久4年)死去。 |
| 22 | 済信 | 954-1030 | 1013- | 東大寺別当64世。勧修寺長吏。東寺長者22世。大安寺別当。金剛峰寺座主15世。954年(天暦8年)生。1013年(長和2年)1月14日、東寺長者。1030年(長元3年)6月11日死去。 |
| 23 | 深覚 | 955-1043 | 1023-1031 | 再任。1023年(治安3年)12月29日、東寺長者。1031年(長元4年)12月26日、東寺長者退任。 |
| 24 | 仁海 | 951-1046 | 1031- | 曼荼羅寺の開山。小野流の祖。随心院8世。雅真の弟子。東大寺別当71世。東寺長者24・26世951年(天暦5年)生。1031年(長元4年)12月26日、東寺長者。1046年(永承1年)死去。 |
| 25 | 深覚 | 955-1043 | 1033- | 再任。1033年(長元6年)12月22日、東寺長者。 |
| 26 | 仁海 | 951-1046 | 1043- | 再任。1043年(長久4年)9月、東寺長者。 |
| 27 | 深観 | 1001-1050 | 1046- | 花山天皇の第四皇子。東大寺別当73世。東寺長者27世。。金剛峰寺座主。禅林寺6世。1001年(長保3年)生または1003年(長保5年)生。1046年(永承1年)、東寺長者。1050年(永承5年)6月15日死去。 |
| 28 | 覚源 | 1000-1065 | 1050- | 花山天皇皇子。禅林寺住職(5世深覚の直後だが、歴代に数えないという)。醍醐寺座主12世。東大寺別当77世。(略歴は醍醐寺#組織を参照) 1000年(長保2年)生。1050年(永承5年)10月24日、東寺長者。1065年(治暦1年)8月18日死去。 |
| 29 | 長信 | ?-1072 | 1065- | 1065年(治暦1年)8月、東寺長者。1072年(延久4年)9月30死去。 |
| 30 | 成尊 | 1012-1074 | 1072- | 随心院9世。東寺長者30世。1012年(長和1年)生。1072年(延久4年)10月、東寺長者。1074年(承保1年)1月7日死去。 |
| 31 | 良深 | 1025-1077 | 1074- | 1025年(万寿2年)生。1074年(承保1年)10月27日、東寺長者。1077年(承暦1年)8月24日死去。 |
| 32 | 信覚 | 1011-1084 | 1075- | 勧修寺長吏。東大寺別当80世。東寺長者32世。仁和寺別当。金剛峰寺座主。1011年(寛弘8年)生。1075年(承保2年)1月14日、東寺長者。1084年(応徳1年)9月15日死去。 |
| 33 | 定賢 | ?-1100 | 1084- | 醍醐寺13世。1084年(応徳1年)9月、東寺長者。1100年(康和2年)10月6日死去。 |
| 34 | 頼観 | 1032-1102 | 1100-1101 | 仁和寺子院徳大寺に住す。1032年(長元5年)生。1100年(康和2年)、東寺長者。1101年(康和3年)4月25日、東寺長者退任。1102年(康和4年)4月6日死去。 |
| 35 | 経範 | 1031-1104 | 1101- | 東大寺別当82世。1031年(長元4年)生。1101年(康和3年)4月25日、東寺長者。1104年(長治1年)3月17日死去。 |
| 36 | 範俊 | 1038-1112 | 1104- | 随心院10世。1038年(長暦2年)生。1104年(長治1年)5月19日、東寺長者。1112年(天永3年)4月24日死去。 |
| 37 | 寛助 | 1057-1125 | 1115- | 東大寺別当85世。仁和寺別当。円教寺別当。東寺長者37世。広隆寺別当。法勝寺別当。1057年(天喜5年)生。1115年(永久3年)4月、東寺長者。1125年(天治2年)1月15日死去。 |
| 38 | 勝覚 | 1057/58-1129 | 1124- | 醍醐寺座主14世。三宝院を創建。源俊房の子。東大寺別当84・86世。東寺長者38世。 (略歴は醍醐寺#組織を参照)1057年(天喜5年)生または1058年(康平1年)生。1124年(天治1年)1月15日、東寺長者。1129年(大治4年)4月1日死去。 |
| 39 | 信証 | 1098-1142 | 1129-1133 | 後三条天皇の孫。輔仁親王の王子。西院流開祖。広隆寺別当。1129年(大治4年)4月、東寺長者。1133年(長承2年)10月5日、東寺長者退任。1142年(康治1年)4月8日死去。 |
| 40 | 定海 | 1074-1149 | 1133-1145 | 三宝院流の祖。醍醐寺座主15世。三宝院2世。円光寺別当。東大寺別当87世。金剛峰寺座主。東寺長者40世。1074年(承保1年)生。1133年(長承2年)10月5日、東寺長者。1145年(久安1年)10月29日、東寺長者退任。1149年(久安5年)死去。 |
| 41 | 寛信 | 1085-1153 | 1145- | 元興寺別当。勧修寺長吏。東大寺別当88世。東寺長者41世。1145年(久安1年)10月19日、東寺長者。1153年(仁平3年)3月17日死去。 |
| 42 | 寛遍 | 1100-1166 | 1150- | 忍辱山流の祖。円成寺再興。源師忠の子。広隆寺別当。東寺長者42世。東大寺別当90世。1100年(康和2年)生。1150年(久安6年)2月7日、東寺長者。1166年(仁安1年)6月30日死去。 |
| 43 | 禎喜 | 1099-1183 | 1166- | 広隆寺別当。東寺長者43世。東大寺別当93世。仁和寺別当、円教寺別当。六勝寺別当。広隆寺別当。1099年(康和1年)生。1166年(仁安1年)7月3日、東寺長者。1183年(寿永2年)10月1日死去。 |
| 44 | 定遍 | 1133-1185 | 1183- | 東大寺別当94世。法勝寺別当。仁和寺別当。東寺長者44世。1133年(長承2年)生。1183年(寿永2年)10月2日、東寺長者。1185年(文治1年)12月18日死去。 |
| 45 | 俊証 | 1106-1192 | 1185- | 東大寺別当96世。東寺長者45世。1106年(嘉承1年)生。1185年(文治1年)12月19日、東寺長者。1192年(建久3年)3月17日死去。 |
| 46 | 覚成 | 1126-1198 | 1192- | 東大寺別当98世。仁和寺門跡。東寺長者46世。1126年(大治1年)生。1192年(建久3年)3月20日、東寺長者。1198年(建久9年)10月21日死去。 |
| 47 | 延果(延杲) | 1124-1206 | 1198- | 東大寺別当100世。東寺長者47世。神護寺別当。1198年(建久9年)10月21日、東寺長者。1206年(建永1年)3月12日死去。 |
| 48 | 印性 | ?-1207 | 1206- | 1206年(建永1年)3月15日、東寺長者。1207年(承元1年)7月3日死去。 |
| 49 | 道尊 | 1175-1228 | 1207-1220 | 以仁王の王子。蓮華光院門跡開山。東大寺別当101・105世。東寺長者49・51世。1175年(安元1年)生。1207年(承元1年)7月5日、東寺長者。1220年(承久2年)12月29日、東寺長者退任。1228年(安貞2年)8月5日死去。(略歴は蓮華光院#組織を参照) |
| 50 | 成宝 | 1159-1227 | 1221-1221 | 勧修寺門跡。元興寺に住す。東寺長者。大安寺別当。東大寺別当102・104世。東寺長者50世。 1159年(平治1年)生。1221年(承久3年)1月1日、東寺長者。1221年(承久3年)11月7日、東寺長者退任。1227年(安貞1年)12月17日死去。(略歴は勧修寺#組織を参照) |
| 51 | 道尊 | 1175-1228 | 1221- | 再任1221年(承久3年)11月7日、東寺長者。 |
| 52 | 親厳 | 1151-1236 | 1228- | 随心院の門跡初代。東寺長者52世。東大寺別当108世。1151年(仁平1年)生。1228年(安貞2年)8月、東寺長者。1236年(嘉禎2年)11月2日死去。 |
| 53 | 定豪 | 1152-1238 | 1236- | 鶴岡八幡宮別当。勝長寿院別当。東寺長者53世。大伝法院座主13世。東大寺別当106世。新熊野検校。1152年(仁平2年)生。1236年(嘉禎2年)12月24日、東寺長者。1238年(暦仁1年)9月24日死去。 |
| 54 | 真恵 | 1279-1347 | 1238- | 東大寺別当109世?。東寺長者54世。石山寺座主?1279年(弘安2年)生。1238年(暦仁1年)9月15日、東寺長者。1239年(延応1年)1月21日死去。 |
| 55 | 覚教 | 1167-1242 | 1239-1240 | 1167年(仁安2年)生。1239年(延応1年)1月21日、東寺長者。1240年(仁治1年)9月日、東寺長者退任。1242年(仁治3年)1月8日死去。 |
| 56 | 良慧 | 1192-1268 | 1240-1242 | 九条兼実の子。東寺長者56・58・60世。「良恵」とも。上乗院住職。東大寺別当110世。1240年(仁治1年)9月16日、東寺長者。1242年(仁治3年)2月23日、東寺長者退任。1266年(文永3年)11月24日死去。? |
| 57 | 厳海 | 1173-1251 | 1242-1243 | 随心院門跡15世。東寺長者57世。1173年(承安3年)生。1242年(仁治3年)2月20日、東寺長者。1243年(寛元1年)1月12日、東寺長者退任。1251年(建長3年)4月25日死去。 |
| 58 | 良慧 | 1192-1268 | 1243- | 再任。1243年(寛元1年)6月20日、東寺長者。 |
| 59 | 実賢 | 1176-1249 | 1248- | 1176年(安元2年)生。1248年(宝治2年)12月29日、東寺長者。1249年(建長1年)3月3日死去。 |
| 60 | 良慧 | 1192-1268 | 1249-1251 | 再任。1249年(建長1年)9月6日、東寺長者。1251年(建長3年)5月28日、東寺長者退任。 |
| 61 | 道乗 | 1215-1273 | 1251-1258 | 頼仁親王の王子。上乗院門跡住職。東寺長者。蓮華光院門跡。1215年(建保3年)生。1251年(建長3年)5月30日、東寺長者。1258年(正嘉2年)2月2日、東寺長者退任。1273年(文永10年)12月11日死去。 |
| 62 | 房円 | 生没年不詳 | 1258-1260 | 仁和寺の僧。1258年(正嘉2年)2月3日、東寺長者。1260年(文応1年)5月5日、東寺長者退任。 |
| 63 | 実瑜 | ?-1264 | 1260-1261 | 1260年(文応1年)5月18日、東寺長者。1261年(弘長1年)●月22日、東寺長者退任。1264年(文永1年)7月6日死去。 |
| 64 | 定親 | 1203-1266 | 1261-1262 | 東大寺別当111世。東寺長者64世。1261年(弘長1年)10月22日、東寺長者。1262年(弘長2年)12月26日、東寺長者退任。1266年(文永3年)9月9日死去。 |
| 65 | 道勝 | ?-1273 | 1262-1266 | 1262年(弘長2年)12月26日、東寺長者。1266年(文永3年)5月日、東寺長者退任。1273年(文永10年)7月13日死去。 |
| 66 | 隆澄 | 1181-1266 | 1266-1266 | 1181年(養和1年)生。1266年(文永3年)5月28日、東寺長者。1266年(文永3年)11月日、東寺長者退任。1266年(文永3年)死去。 |
| 67 | 道融 | 1224-1281 | 1266- | 東大寺別当115世。東寺長者67世。蓮華光院。1266年(文永3年)12月5日、東寺長者。1281年(弘安4年)閏7月15日死去。 |
| 68 | 道宝 | 1214-1281 | 1277-1278 | 東大寺別当117世。東寺長者68世。大安寺別当。1214年(建保2年)生。1277年(建治3年)1月11日、東寺長者。1278年(弘安1年)7月4日、東寺長者退任。1281年(弘安4年)8月7日死去。 |
| 69 | 奝助 | 1217-1290 | 1278-1280 | 1217年(建保5年)生。1278年(弘安1年)7月6日、東寺長者。1280年(弘安3年)8月10日、東寺長者退任。1290年(正応3年)12月26日死去。 |
| 70 | 定済 | 1220-1282 | 1280- | 東大寺別当114世。醍醐寺座主37・39世。三宝院門跡12世。東寺長者70世。(略歴は醍醐寺#組織参照) 1220年(承久2年)生。1280年(弘安3年)8月6日、東寺長者。1282年(弘安5年)10月3日死去。 |
| 71 | 勝信 | 1235-1287 | 1282-1284 | 東大寺別当118世。東寺長者71世。勧修寺長吏。1282年(弘安5年)10月14日、東寺長者。1284年(弘安7年)4月20日、東寺長者退任。1287年(弘安10年)7月4日死去。 |
| 72 | 道耀 | 1234-1304 | 1284-1284 | 1234年(文暦1年)生。1284年(弘安7年)4月22日、東寺長者。1284年(弘安7年)11月14日、東寺長者退任。1304年(嘉元2年)12月2日死去。 |
| 73 | 了遍 | 1223-1311 | 1285-1287 | 東大寺別当120世?。東寺長者73世。1223年(貞応2年)生。1285年(弘安8年)11月16日、東寺長者。1287年(弘安10年)8月29日、東寺長者退任。1311年(応長1年)死去。? |
| 74 | 守助 | ?-1294 | 1287-1289 | 1287年(弘安10年)9月3日、東寺長者。1289年(正応2年)11月22日、東寺長者退任。1294年(永仁2年)5月5日死去。 |
| 75 | 静厳 | 1243-1299 | 1289-1292 | 醍醐寺座主44世。東寺長者75世。随心院19世。1243年(寛元1年)生。1289年(正応2年)12月6日、東寺長者。1292年(正応5年)1月5日、東寺長者退任。1299年(正安1年)1月4日死去。 |
| 76 | 実宝 | 生没年不詳 | 1292-1294 | 1292年(正応5年)12月3日、東寺長者。1294年(永仁2年)2月日、東寺長者退任。 |
| 77 | 禅助 | 1247-1330 | 1294-1294 | 大伝法院座主20世。東寺長者77・88・96世。神護寺別当。1247年(宝治1年)生。1294年(永仁2年)2月7日、東寺長者。1294年(永仁2年)7月日、東寺長者退任。1330年(元徳2年)死去。 |
| 78 | 勝恵 | ?-1299 | 1294-1297 | 1294年(永仁2年)11月21日、東寺長者。1297年(永仁5年)3月24日日、東寺長者退任。1299年(正安1年)2月8日死去。 |
| 79 | 守恵 | 生没年不詳 | 1297-1298 | 1297年(永仁5年)3月26日、東寺長者。1298年(永仁6年)5月20日、東寺長者退任。 |
| 80 | 守誉 | 生没年不詳 | 1298-1298 | 1298年(永仁6年)5月25日、東寺長者。1298年(永仁6年)10月29日、東寺長者退任。 |
| 81 | 深快 | 生没年不詳 | 1298-1299 | 1298年(永仁6年)11月3日、東寺長者。1299年(正安1年)1月4日、東寺長者退任。 |
| 82 | 守瑜 | 生没年不詳 | 1299-1300 | 1299年(正安1年)、東寺長者。1300年(正安2年)2月7日、東寺長者退任。 |
| 83 | 守誉 | ?-1304 | 1300-1300 | 1300年(正安2年)2月8日、東寺長者。1300年(正安2年)閏7月27日、東寺長者退任。1304年(嘉元2年)5月19日死去。 |
| 84 | 長遍 | 1223-1302 | 1300-1300 | 1223年(貞応2年)生。1300年(正安2年)4月22日、東寺長者。1300年(正安2年)日、東寺長者退任。1302年(乾元1年)死去。 |
| 85 | 信忠 | ?-1322 | 1300-1305 | 勧修寺門跡。東寺長者85世。東大寺別当125世。1300年(正安2年)、東寺長者。1305年(嘉元3年)2月10日、東寺長者退任。1322年(元亨2年)10月19日死去。 |
| 86 | 厳家 | 1275-1308 | 1303-1306 | 摂政一条家経の子。醍醐寺座主50世。東寺長者86世。随心院20世。1275年(建治1年)生。1303年(嘉元1年)2月24日、東寺長者。1306年(徳治1年)8月15日、東寺長者退任。1308年(延慶1年)11月3日死去。 |
| 87 | 親玄 | 1249-1322 | 1306-1307 | 1249年(建長1年)生。1306年(徳治1年)11月18日、東寺長者。1307年(徳治2年)10月3日、東寺長者退任。1322年(元亨2年)2月17日死去。 |
| 88 | 禅助 | 1247-1330 | 1307-1308 | 再任。1247年(宝治1年)生。1307年(徳治2年)12月3日、東寺長者。1308年(延慶1年)3月16日、東寺長者退任。1330年(元徳2年)2月12日死去。 |
| 89 | 聖忠 | 1268-1319 | 1308-1310 | 東大寺別当121世・124世・127世。醍醐寺座主51世。東寺長者89世。法務。(略歴は醍醐寺#組織を参照) 1268年(文永5年)生。1308年(延慶1年)3月21日、東寺長者。1310年(延慶3年)7月3日、東寺長者退任。1319年(元応1年)死去。 |
| 90 | 成恵 | ?-1315 | 1310-1311 | 安祥寺に住す。1310年(延慶3年)7月4日、東寺長者。1311年(応長1年)12月10日、東寺長者退任。1315年(正和4年)12月23日死去。 |
| 91 | 定助 | 1263-1346 | 1311-1313 | 仁和寺尊勝院住職。神護寺別当。東寺長者91世。1311年(応長1年)12月10日、東寺長者。1313年(正和2年)1月2日、東寺長者退任。 |
| 92 | 能助 | ?-1324 | 1313- | 1313年(正和2年)1月6日、東寺長者。1324年(正中1年)5月2日死去。 |
| 93 | 実海 | 1269-1318 | 1315-1317 | 東大寺別当126世。東寺長者93世。1269年(文永6年)生。1315年(正和4年)10月、東寺長者。1317年(文保1年)4月日、東寺長者退任。1318年(文保2年)5月7日死去。 |
| 94 | 顕誉 | 1275-1325 | 1317-1318 | 1275年(建治1年)生。1317年(文保1年)4月3日、東寺長者。1318年(文保2年)12月29日、東寺長者退任。1325年(正中2年)9月7日死去。 |
| 95 | 公紹 | ?-1321 | 1319- | 姉小路実世の子。1319年(元応1年)、東寺長者。1321年(元亨1年)8月10日死去。 |
| 96 | 禅助 | 1247-1330 | 1319-1320 | 再任。1247年(宝治1年)生。1319年(元応1年)8月19日、東寺長者。1320年(元応2年)7月日、東寺長者退任。1330年(元徳2年)死去。 |
| 97 | 道順 | ?-1321 | 1320- | 久我通光の孫。醍醐寺57世。1320年(元応2年)7月22日、東寺長者。1321年(元亨1年)12月28日死去。 |
| 98 | 実弘 | 生没年不詳 | 1321-1322 | 1321年(元亨1年)12月25日、東寺長者。1322年(元亨2年)12月25日、東寺長者退任。 |
| 99 | 弘舜 | 生没年不詳 | 1322-1323 | 1322年(元亨2年)12月29日、東寺長者。1323年(元亨3年)11月30日、東寺長者退任。 |
| 100 | 教寛 | 生没年不詳 | 1323-1325 | 勧修寺長吏。東大寺別当129・131世。東寺長者100世。1323年(元亨3年)11月30日、東寺長者。1325年(正中2年)8月22日、東寺長者退任。 |
| 101 | 有助 | 1277-1333 | 1325-1326 | 1277年(建治3年)生。1325年(正中2年)11月25日、東寺長者。1326年(嘉暦1年)2月9日、東寺長者退任。1333年(元弘3年/正慶2年)死去。 |
| 102 | 道意 | 1290-1356 | 1326- | 1290年(正応3年)生。1326年(嘉暦1年)2月9日、東寺長者。1356年(正平11年/延文1年)死去。 |
| 103 | 教寛 | 生没年不詳 | 1326- | 再任。1326年(嘉暦1年)、東寺長者。 |
| 104 | 聖尋 | 生没年不詳 | 1328- | 東大寺別当130世。東寺長者104・106世。醍醐寺座主59・61世。三宝院門跡20世。伝法院座主。1328年(嘉暦3年)、東寺長者。 |
| 105 | 賢助 | 1280-1333 | 1328- | 1280年(弘安3年)生。1328年(嘉暦3年)12月30日、東寺長者。1333年(元弘3年/正慶2年)死去。 |
| 106 | 聖尋 | 生没年不詳 | 1329- | 再任。1329年(元徳1年)3月8日、東寺長者。 |
| 107 | 道意 | 1290-1356 | 1331- | 再任。1290年(正応3年)生。1331年(元徳3年)、東寺長者。1356年(正平11年/延文1年)死去。 |
| 108 | 益守 | 生没年不詳 | 1332- | 1332年(元弘2年)1月2日、東寺長者。 |
| 109 | 成助 | 生没年不詳 | 1332-1333 | 1332年(元弘2年)12月23日、東寺長者。1333年(正慶2年)東寺長者退任。 |
| 110 | 道意 | 1290-1356 | 1333- | 再任。1290年(正応3年)生。1333年(正慶2年)、東寺長者。1356年(正平11年/延文1年)死去。 |
| 111 | 益守 | 生没年不詳 | 1334- | 1334年(建武1年)12月30日、東寺長者。 |
| 112 | 弘真 | 1278-1357 | 1335- | 1278年(弘安1年)生。1335年(建武2年)3月15日、東寺長者。1357年(正平12年/延文2年)死去。 |
| 113 | 成助 | 生没年不詳 | 1336- | 再任。1336年(延元1年/建武3年)9月16日、東寺長者。 |
| 114 | 賢俊 | 1299-1357 | 1340- | 1299年(正安1年)生。1340年(興国1年/暦応3年)12月26日、東寺長者。1357年(正平12年/延文2年)死去。 |
| 115 | 経厳 | ?-1353 | 1342- | 摂政一条家経の子。厳家の弟。東寺長者115世。随心院21世。1342年(興国3年/康永1年)2月12日、東寺長者。 |
| 116 | 賢俊 | 1299-1357 | 1342- | 再任。1299年(正安1年)生。1342年(興国3年/康永1年)3月19日、東寺長者。1357年(正平12年/延文2年)死去。 |
| 117 | 栄海 | 1278-1347 | 1345- | 勧修寺慈尊院住職。神護寺別当。東寺長者117世。1278年(弘安1年)生。1345年(興国6年/貞和1年)1月4日、東寺長者。1347年(正平2年/貞和3年)死去。 |
| 118 | 賢俊 | 1299-1357 | 1345- | 再任。1299年(正安1年)生。1345年(興国6年/貞和1年)11月29日、東寺長者。1357年(正平12年/延文2年)死去。 |
| 119 | 隆舜 | 1280-1353 | 1350- | 1280年(弘安3年)生。1350年(正平5年/観応1年)11月27日、東寺長者。1353年(正平8年/文和2年)1月14日死去。 |
| 120 | 弘真 | 1278-1357 | 1351- | 再任。1278年(弘安1年)生。1351年(正平6年/観応2年)11月、東寺長者。1357年(正平12年/延文2年)死去。 |
| 121 | 道意 | 1290-1356 | 1353- | 再任。1290年(正応3年)生。1353年(正平8年/文和2年)、東寺長者。1356年(正平11年/延文1年)死去。 |
| 122 | 聖珍法親王 | ?-1382 | 1354- | 伏見天皇皇子。東大寺別当132・137・139世。東寺長者122世。醍醐寺座主69世。 三宝院門跡23世。1354年(正平9年/文和3年)9月28日、東寺長者。1382年(弘和2年/永徳2年)死去。 |
| 123 | 定憲 | ?-1264 | 1356-1359 | 東寺長者123・126・128世。1356年(正平11年/延文1年)6月28日、東寺長者。1359年(延文4年)4月10日、東寺長者退任。1264年(文永1年)死去。 |
| 124 | 覚雅 | 生没年不詳 | 1359-1384 | 醍醐寺報恩院。1359年(正平14年/延文4年)4月12日、東寺長者。1384年(至徳1年)12月日、東寺長者退任。 |
| 125 | 光済 | 1326-1379 | 1360- | 東寺長者125・127・129世。1326年(嘉暦1年)生。1360年(正平15年/延文5年)12月29日、東寺長者。1379年(天授5年/康暦1年)閏4月22日死去。 |
| 126 | 定憲 | ?-1264 | 1367- | 再任。1367年(正平22年/貞治6年)5月、東寺長者。 |
| 127 | 光済 | 1326-1379 | 1372- | 再任。1372年(文中1年/応安5年)、東寺長者。 |
| 128 | 定憲 | ?-1264 | 1374- | 再任。1374年(文中3年/応安7年)4月、東寺長者。 |
| 129 | 光済 | 1326-1379 | 1375- | 再任。1375年(天授1年/永和1年)2月10日、東寺長者。 |
| 130 | 宗助 | 生没年不詳 | 1379- | 東寺長者130・132世。1379年(天授5年/康暦1年)6月、東寺長者。 |
| 131 | 道快 | 1209-1248 | 1384- | 東大寺東南院。藤原道経の子。東寺長者法務。醍醐寺地蔵院を中興。「聖快」「快賢」とも名乗った。 1384年(元中1年/至徳1年)12月29日、東寺長者。 |
| 132 | 宗助 | 生没年不詳 | 1390- | 再任。1390年(元中7年/明徳1年)、東寺長者。 |
| 133 | 俊尊 | 生没年不詳 | 1395- | 1395年(応永2年)12月30日、東寺長者。 |
| 134 | 満済 | 1378-1435 | 1409- | 東寺長者134・141世。1378年(天授4年/永和4年)生。1409年(応永16年)8月3日、東寺長者。1435年(永享7年)死去。 |
| 135 | 守融 | 生没年不詳 | 1411-1412 | 東寺長者135・137世。1411年(応永18年)4月5日、東寺長者。1412年(応永19年)1月16日、東寺長者退任。 |
| 136 | 隆源 | 1342-1426 | 1412- | 1342年(興国3年/康永1年)生。1412年(応永19年)2月8日、東寺長者。1426年(応永33年)死去。 |
| 137 | 守融 | 生没年不詳 | 1413- | 再任。1413年(応永20年)6月12日、東寺長者。 |
| 138 | 禅守 | 1333-? | 1414- | 邦省親王の王子。仁和寺で学ぶ。1333年(元弘3年/正慶2年)生。1414年(応永21年)5月3日、東寺長者。 |
| 139 | 祐厳 | ?-1452 | 1415- | 関白一条経嗣の子。随心院25世。東寺長者139・150・159世。1415年(応永22年)2月10日、東寺長者。1452年(享徳1年)死去。 |
| 140 | 超済 | ?-1416 | 1416- | 1416年(応永23年)9月22日、東寺長者。1416年(応永23年)10月3日死去。 |
| 141 | 満済 | 1378-1435 | 1416- | 再任。1416年(応永23年)10月9日、東寺長者。 |
| 142 | 光超 | 生没年不詳 | 1421- | 1421年(応永28年)、東寺長者。 |
| 143 | 房教 | 生没年不詳 | 1421- | 東寺長者143・146世。1421年(応永28年)4月10日、東寺長者。 |
| 144 | 義昭 | 生没年不詳 | 1421- | 将軍・足利義満の子。東寺長者144・149世。大覚寺門跡31世。 蓮華光院。東寺長者144・149世。反乱を起こし、島津に討たれる。永徳寺(宮崎県)などに墓。 1421年(応永28年)8月、東寺長者。 |
| 145 | 実順 | 生没年不詳 | 1422- | 1422年(応永29年)12月26日、東寺長者。 |
| 146 | 房教 | 生没年不詳 | 1424- | 再任。1424年(応永31年)6月2日、東寺長者。 |
| 147 | 義賢 | 1399-1468 | 1426- | 足利満詮の子。東寺長者147・167世。醍醐寺74世。三宝院門跡26世。1399年(応永6年)生。1426年(応永33年)12月5日、東寺長者。1468年(応仁2年)死去。 |
| 148 | 禅信 | 生没年不詳 | 1426- | 東寺長者148・154・156・164・165世。1426年(応永33年)12月、東寺長者。 |
| 149 | 義昭 | 生没年不詳 | 1427- | 再任。1427年(応永34年)3月20日、東寺長者。 |
| 150 | 祐厳 | ?-1452 | 1428- | 再任。1428年(正長1年)5月6日、東寺長者。1452年(享徳1年)死去。 |
| 151 | 成基 | 生没年不詳 | 1430- | 1430年(永享2年)12月17日、東寺長者。 |
| 152 | 宗観 | ?-1447 | 1431- | 1431年(永享3年)12月8日、東寺長者。1447年(文安4年)死去。 |
| 153 | 持円 | 生没年不詳 | 1432- | 足利満詮の子。東寺長者153世。日輪寺別当。1432年(永享4年)12月18日、東寺長者。 |
| 154 | 禅信 | 生没年不詳 | 1433- | 再任。1433年(永享5年)10月11日、東寺長者。 |
| 155 | 賢快 | 生没年不詳 | 1434- | 1434年(永享6年)6月23日、東寺長者。 |
| 156 | 禅信 | 1434- | 再任。1434年(永享6年)7月13日、東寺長者。 | |
| 157 | 弘継 | 1434- | 1434年(永享6年)12月11日、東寺長者。 | |
| 158 | 成淳 | 1438- | 1438年(永享10年)11月12日、東寺長者。 | |
| 159 | 祐厳 | ?-1452 | 1439- | 再任。1439年(永享11年)12月13日、東寺長者。1452年(享徳1年)死去。 |
| 160 | 定意 | 1441- | 1441年(嘉吉1年)10月11日、東寺長者。 | |
| 161 | 守遍 | 1448- | 1448年(文安5年)12月18日、東寺長者。 | |
| 162 | 了助 | 1450- | 1450年(宝徳2年)12月17日、東寺長者。 | |
| 163 | 賢性 | 1453- | 1453年(享徳2年)8月9日、東寺長者。 | |
| 164 | 禅信 | 1457-1459 | 再任。1457年(長禄1年)10月16日、東寺長者。1459年(長禄3年)12月9日、東寺長者退任。 | |
| 165 | 禅信 | 1460- | 再任。1460年(寛正1年)4月19日、東寺長者。 | |
| 166 | 宗済 | 1460- | 1460年(寛正1年)10月8日、東寺長者。 | |
| 167 | 義賢 | 1399-1468 | 1463- | 再任。1463年(寛正4年)10月29日、東寺長者。 |
| 168 | 定昭 | 1465- | 1465年(寛正6年)8月28日、東寺長者。 | |
| 169 | 厳宝 | ?-1481 | 1466- | 一条兼良の子。随心院門跡26世。東大寺別当163世。東寺長者169世。1466年(文正1年)4月11日、東寺長者。 |
| 170 | 隆済 | 1469- | 1469年(文明1年)6月2日、東寺長者。 | |
| 171 | 守鑁 | ?-1483 | 1483- | 1483年(文明15年)6月20日、東寺長者。1483年(文明15年)12月21日死去。 |
| 172 | 性深 | 生没年不詳 | 1488- | 大覚寺門跡。1488年(長享2年)11月10日、東寺長者。 |
| 173 | 賢深 | 1502-1504 | 1502年(文亀2年)12月18日、東寺長者。1504年(永正1年)1月29日、東寺長者退任。 | |
| 174 | 持厳 | 1508-1510 | 三宝院門跡30世。醍醐寺座主78世。 随心院門跡27世。1508年(永正5年)7月8日、東寺長者。1510年(永正7年)12月28日、東寺長者退任。 | |
| 175 | 義堯 | 1534-1536 | 三宝院門跡31世。醍醐寺座主79世。1534年(天文3年)1月26日、東寺長者。1536年(天文5年)9月5日、東寺長者退任。1564年(永禄7年)2月15日死去。 | |
| 176 | 源雅 | ?-1562 | 1543- | 1543年(天文12年)4月5日、東寺長者。1562年(永禄5年)12月8日死去。 |
| 177 | 堯雅 | ?-1592 | 1581- | 1581年(天正9年)3月16日、東寺長者。1592年(文禄1年)10月8日死去。 |
| 178 | 義演 | 1558-1626 | 1594- | 醍醐寺中興。醍醐寺座主80世。関白三条晴良の子。三宝院門跡32世。大伝法院座主。東寺長者178世。豊臣秀吉の帰依を受ける。後七日御修法を復興。 1594年(文禄3年)7月16日、東寺長者。1626年(寛永3年)死去。 |
| 179 | 堯円 | 1626- | 1626年(寛永3年)12月28日、東寺長者。 | |
| 180 | 増孝 | 1589-1644 | 1630- | 関白九条兼孝の子。東大寺別当176世。随心院門跡31世。東寺長者180世。1630年(寛永7年)12月24日、東寺長者。1644年(正保1年)死去。 |
| 181 | 尊性法親王 | 1602-1651 | 1635- | 後陽成天皇皇子。大覚寺門跡37世。1635年(寛永12年)4月21日、東寺長者。 |
| 182 | 寛海 | 1651- | 1651年(慶安4年)8月2日、東寺長者。 | |
| 183 | 寛済 | 1658- | 1658年(万治1年)5月20日、東寺長者。 | |
| 184 | 信遍 | 1663- | 1663年(寛文3年)8月7日、東寺長者。 | |
| 185 | 高賢 | ?-1707 | 1666- | 三宝院34世。鷹司教平の子。大峰山入峰。『鳳閣寺縁起』を著す。宝池院大僧正。 1666年(寛文6年)7月22日、東寺長者。1707年(宝永4年)死去。 |
| 186 | 性演 | 1610-1674 | 1670- | 蓮華光院中興。東大寺尊勝院院主。1670年(寛文10年)11月3日、東寺長者。1674年(延宝2年)死去。 |
| 187 | 永愿 | 1672- | 1672年(寛文12年)4月5日、東寺長者。 | |
| 188 | 有雅 | 1678- | 1678年(延宝6年)8月28日、東寺長者。 | |
| 189 | 孝源 | 1684- | 1684年(貞享1年)4月12日、東寺長者。 | |
| 190 | 頼遍 | 1690- | 1690年(元禄3年)8月10日、東寺長者。 | |
| 191 | 了海 | 1695- | 1695年(元禄8年)5月27日、東寺長者。 | |
| 192 | 隆証 | 1702- | 1702年(元禄15年)4月5日、東寺長者。 | |
| 193 | 房演 | 1706- | 三宝院35世。1706年(宝永3年)6月8日、東寺長者。 | |
| 194 | 寛順 | 1711- | 1711年(正徳1年)10月3日、東寺長者。 | |
| 195 | 道恕 | 1668-1733 | 1718- | 久我広道の子。東大寺別当180世。東寺長者195・197世。蓮華光院門跡。尊勝院、華厳長吏。1718年(享保3年)3月28日、東寺長者。1733年(享保18年)死去。 |
| 196 | 堯観 | 1723- | 1723年(享保8年)8月10日、東寺長者。 | |
| 197 | 道恕 | 1668-1733 | 1729- | 再任。1729年(享保14年)8月28日、東寺長者。 |
| 198 | 了恕 | 1733- | 1733年(享保18年)11月12日、東寺長者。 | |
| 199 | 孝宥 | 1736- | 1736年(元文1年)5月12日、東寺長者。 | |
| 200 | 隆幸 | 1737- | 1737年(元文2年)5月18日、東寺長者。 | |
| 201 | 栄遍 | 1746- | 1746年(延享3年)5月2日、東寺長者。 | |
| 202 | 実雅 | 1751- | 1751年(宝暦1年)3月12日、東寺長者。 | |
| 203 | 元雅 | 1756- | 1756年(宝暦6年)8月17日、東寺長者。 | |
| 204 | 寛深 | 1762- | 大覚寺41世。1762年(宝暦12年)2月14日、東寺長者。 | |
| 205 | 道証 | 1764- | 1764年(明和1年)10月2日、東寺長者。 | |
| 206 | 宥証 | 1766- | 1766年(明和3年)3月28日、東寺長者。 | |
| 207 | 尊淳 | 1766- | 東寺長者207・211世。1766年(明和3年)9月19日、東寺長者。 | |
| 208 | 果観 | 1774- | 1774年(安永3年)7月29日、東寺長者。 | |
| 209 | 寛証 | 1776- | 1776年(安永5年)3月16日、東寺長者。 | |
| 210 | 宥証 | 1774- | 1774年(安永3年)10月10日、東寺長者。 | |
| 211 | 尊淳 | 1786- | 再任。1786年(天明6年)5月6日、東寺長者。 | |
| 212 | 禅証 | 1786- | 東寺長者212・214世。1786年(天明6年)7月13日、東寺長者。 | |
| 213 | 寛淳 | 1790- | 1790年(寛政2年)11月4日、東寺長者。 | |
| 214 | 禅証 | 1794- | 再任。1794年(寛政6年)12月11日、東寺長者。 | |
| 215 | 高演 | 1765-1848 | 1802- | 鷹司輔平の子。東寺長者215世。三宝院42世。後自在院。1802年(享和2年)10月、東寺長者。 |
| 216 | 禅豪 | 1807- | 1807年(文化4年)12月25日、東寺長者。 | |
| 217 | 果助 | 1813- | 1813年(文化10年)8月26日、東寺長者。 | |
| 218 | 亮深 | 1816- | 大覚寺43世。1816年(文化13年)8月、東寺長者。 | |
| 219 | 禅忍 | 1818- | 1818年(文政1年)7月1日、東寺長者。 | |
| 220 | 深融 | 1823- | 1823年(文政6年)12月1日、東寺長者。 | |
| 221 | 良助 | 1827- | 1827年(文政10年)7月17日、東寺長者。 | |
| 222 | 淳心 | 1827- | 1827年(文政10年)10月24日、東寺長者。 | |
| 223 | 高演 | 1765-1848 | 1831- | 1831年(天保2年)3月28日、東寺長者。1848年(嘉永1年)死去。 |
| 224 | 寛恕 | 1835- | 1835年(天保6年)10月29日、東寺長者。 | |
| 225 | 増護 | 1804-1875 | 東大寺別当188世。左大臣二条治孝の子。随心院門跡35世。東寺長者225世。東南院門跡。三宝院48世。1875年(明治8年)死去。 |
東寺長者(近代)
- 226冷泉元誉(-1890)<>:1879年(明治12年)6月仁和寺門跡。1890年(明治23年)死去。
- 227大宮覚宝()<>:観智院17世。権大教正。
- 228三条西乗禅(1844-1888)<-1886>:観智院18世。権大教正。真言宗管長。後七日御修法の再興をはかる。1886年6月10日東寺長者退任。著書『在家勤行法則』。1888年8月3日死去。45歳。
- 229別所栄厳(1814-1900)<1888-1890>:勧修寺長吏。仁和寺門跡。淡路国津名郡出身。俗姓は上撫氏。1814年(文化11年)1月3日生。青蓮寺教栄に師事して出家。1827年(文政10年)四度加行。1828年(文政11年)春、高野山に登る。西南院隆快に灌頂を受ける。1834年(天保5年)高野山に交衆。1838年(天保9年)青蓮寺住職となるがまもなく辞任して高野山の再び登る。真別処隆鎮に師事。1862年(文久2年)真別処に僧堂を建てる。1878年(明治11年)春、勧修寺長吏。1880年(明治13年)春、大教正。1883年(明治16年)1月8日、再興された後七日御修法の大阿闍梨を務めた。1884年(明治17年)秋、仁和寺門跡。1888年(明治21年)7月1日真言宗長者就任(官報1512同月14日号)。1890年7月1日東寺長者退任。1900年(明治33年)12月28日死去。87歳。(「明治以降野峯高僧伝」)
- 230松平実因(1820-1889)<1886-1888>:智積院化主42世。1820年(文政3年)生。1886年6月10日東寺長者就任。1888年6月25日東寺長者退任。1889年(明治22年)死去。
- 231楠玉諦(1828-1912)<1892->:大覚寺門跡。1892年7月1日東寺長者就任。著書『高野山大塔興廃略記』。
- 232原心猛(1833-1906)<1890-1892,>:金剛峰寺座主384世。東寺長者254世(?)。出雲国出雲郡出身。1833年(天保4年)生。龍光院住職58世。1899年(明治32年)真言宗連合総裁。1906年(明治39年)5月6日死去。74歳。1834年(天保5年)10月28日生。8歳で高野寺恵深に師事して出家。1847年(弘化4年)岩屋寺宣明のもとで四度加行。1852年(嘉永5年)高野山普賢院で実賢から伝法灌頂。1863年(文久3年)岩倉寺住職。1865年(慶応1年)高野山に再び登る。1871年(明治4年)出雲千手院住職。1873年(明治6年)教導職大講義。1875年(明治8年)大教院庶務課長。1880年(明治13年)金剛峰寺出張所庶務課長兼感得。権少教正。1884年(明治17年)空海1050年御忌奉修総裁。龍光院住職。桜池院住職。1886年(明治19年)権中僧正。法務所課長。1889年(明治22年)金剛峰寺座主となり、中僧正、大学林総理。1890年(明治23年)大僧正。同年7月1日、真言宗長者。東寺住職を兼務。金剛峰寺と東寺の兼務は観賢以来という。1892年7月1日東寺長者退任。1897年(明治30年)、金剛峰寺の寺務検校執行法印大和尚位397世に就任。1899年(明治32年)東寺長者250世再任(?)。1900年(明治33年)高野派管長。真言宗連合総裁。1905年(明治38年)管長退任。1906年(明治39年)5月6日、龍光院で死去。73歳。(「明治以降野峯高僧伝」)
- 233高志大了(1834-1898)<>:長谷寺化主55世。1834年(天保5年)生。1898年(明治31年)死去。
- 234鼎龍暁()<>:泉涌寺長老。勧修寺長吏。観智院19世。1897年(明治30年)10月30日任期満了で真言宗長者を退任(官報28日付。内務省、26日認可)。
- 235三神快運(1836-1905)<>:智積院化主46世。1836年(天保7年)生。1897年(明治30年)10月30日真言宗長者に就任(官報28日付。内務省、26日認可)。1905年(明治38年)死去。
- 236長宥匡(1838-1917)<>:勧修寺長吏。1900年8月21日真言宗連合長者に就任。1917年(大正6年)1月11日死去。
- 237高幢龍暢(1827-1912)<>:大覚寺門跡。1827年(文政10年)生。1912年(大正1年)死去。
- 238土宜法龍(1854-1923)<-1912->:尾張出身。1854年(安政1年)生。仁和寺門跡、金剛峰寺座主を歴任。南方熊楠と交流。1923年(大正12年)1月10日死去。70歳。
(『日本仏家人名辞書』)
- 密門宥範()<>:1915年5月16日真言宗連合総裁となる。
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250鎌田観応(1849-1923)<1905->:尾張藩士松下勘十郎の三男。1849年(嘉永2年)5月11日生。1860年(万延1年)播磨百代寺で出家。17歳で高野山で学ぶ。高野山大学林で教える。1899年(明治32年)宝性院門主。清浄心院、実城院、丹生院、智荘厳院に住す。1904年(明治37年)金剛峰寺の寺務検校執行法印大和尚位404世に就任 。1905年(明治38年)東寺法主。東寺派管長。1923年(大正12年)高野派管長・金剛峰寺座主となった。真言宗連合総裁。1923年(大正12年)8月8日死去。東寺長者250世。(20世紀日本人名事典)(「明治以降野峯高僧伝」)
- 251?松永昇道(1866-1942)<1923->:観智院21世。岐阜県出身。1866年(慶応2年)生。1888年(明治21年)高野山大学卒(1期生)。1923年(大正12年)東寺法主、大僧正。1942年(昭和17年)死去。
- 252?日下義禅(-1956?)<-1950>:大阪了徳院住職。1919年(大正8年)、別院として宝塚聖天を創建。
- 253?山本忍梁(-1956)<1950-1956>:1950年(昭和25年)就任。1956年(昭和31年)死去。著書『東寺沿革略誌』。
- 254?木村澄覚(1889-1975)<1957-1975>:香川県出身。1889年(明治22年)3月5日生。真行寺で出家。早稲田大学卒業。1931年(昭和6年)、東寺に入る。高野山上海別院主管。東寺観智院住職。1957年(昭和32年)、東寺長者。真言宗京都学園理事長。1975年(昭和50年)12月30日死去。86歳。(20世紀日本人名事典)
- 255?鷲尾隆輝(1917-2004)<1974-2004>:初代東寺真言宗管長。石山寺座主。1917年(大正6年)12月17日生。男爵鷲尾光遍の子。曽祖父は1866年(慶応2年)12月、突如、勤王志士を引き連れて高野山に登った鷲尾隆聚(のち伯爵)。1967年、石山寺座主。1974年(昭和49年)東寺真言宗管長。2004年(平成16年)10月15日死去。88歳。西国三十三所札所会会長。
- 256砂原秀遍(1925-2019)<2004-2019>:島根県隠岐出身。1937年、隠岐国分寺で得度。1940年薬王寺で四度加行成満。1945年徴兵されて中国戦線に出兵。1947年4月、隠岐国分寺住職。1957年に東寺に入る。1988年、東寺責任役員。1992年東寺事務長(代表役員)。2004年11月18日、東寺長者・東寺真言宗管長2世。2019年7月6日、在職で死去。94歳。
- 257飛鷹全隆()<2020->:金剛峰寺寺務検校執行法印520世。2020年7月21日から4年間。
真言宗連合長者
- 1長宥匡
- 2高幢龍暢
- 3土宜法龍
- 4密門宥範
- 5土宜法龍
真言宗連合総裁
- 1密門宥範
- 2土宜法龍
- 3鎌田観応
- 4泉智等
東寺座主
- 禅助(1247-1330):後宇多法皇に灌頂を授けた褒賞として1308年(延慶1年)初代東寺座主となる。のち東寺一長者。
- 道意(1290-1356):1334年(建武1年)、五重塔再建の功績で東寺座主となる。東寺長者。
東寺別当
宝菩提院が兼務することも。
- 聖宝(832-909):
- 益信(827-906):894年(寛平6年)東寺別当。
- 会理(852-935):915年(延喜15年)東寺凡僧別当。877年(元慶1年)東寺二長者。929年(延長7年)東寺別当。
- 時円:1091年(寛治5年)在職。
- 頼意:1334年(建武1年)在職。日野僧正。
東寺凡僧別当
真紹が任命された「東寺少別当」を前身とする説もある。
- 春孝:『東宝記』によると初代凡僧別当。真済の弟子。
- 観賢(854-925):900年(昌泰3年)東寺凡僧別当。
- 会理(852-935):915年(延喜15年)東寺凡僧別当。877年(元慶1年)東寺二長者。929年(延長7年)東寺別当。
- 元杲(914-995):972年(天禄3年)東寺凡僧別当。
- 仁海(951-1046):東寺凡僧別当。のち東寺一長者。
東寺執行
東寺執行。修理別当とも。空海の母の出身氏族である阿刀氏(物部氏の系統)が世襲した。京都国立博物館に「阿刀家伝世資料」が所蔵される。『東寺執行日記』を書き継いできた。
- 永真()<>:
- 慶秀()<>:
- 忠救()<>:1330年(元徳2年)在職
- 定伊()<>:1362年(正平17年/貞治1年)在職
- 栄暁()<>:1406年(応永13年)在職
- 栄増()<1431-1454>:1431年(永享3年)在職。初名は厳暁。執行職に伝えられた記録を編纂して多数の文献を残した。『東宝記』の写本(国宝)を書写。『東寺執行日記』を項目別に整理し、1490年頃に『東寺私用集』を編纂。『王代年代記』。
- 栄清()<>:1540年(天文9年)在職。
- 厳伊()<>:
- 隆盛()<>:1357年(正平12年/延文2年)在職。
- 定俊()<>:1115年(永久3年)在職。
- 慶増(?-1867)<>:都城六勇士を弔った後、自らも自刃した。墓は都城六勇士墓地にある。
執事長
宗教法人東寺の代表役員。寺務長、事務長と称した時期もある。東寺真言宗の宗教総長は別。
- 松永昇道(1866-1942)<1905->:東寺長者。
- 長無関()<>:
- 田中清澄(-1985)<>:真言宗東寺派宗務長。管長代務者。
- 三浦俊良(1913-2010)<1971-1972>:自坊は宝菩提院。大分県竹田市出身。1929年(昭和4年)、高野山で得度。上海別院で開教に従事。1942年(昭和17年)東寺入寺。1956年(昭和31年)、宝菩提院住職。1971年(昭和46年)から翌年まで事務長。真言宗東寺派からの離脱に道筋を付けた。洛南高校の改革に尽力。2010年(平成22年)6月24日死去。97歳。洛南高等学校校長。
- 鷲尾隆輝(1917-2004)<1972-1974>:自坊は石山寺。東寺長者。初代東寺真言宗管長。石山寺座主。
- 岩橋政寛(-2001)<1974-1992>:自坊は観智院。1974年(昭和49年)10月25日、東寺真言宗の設立に合わせて事務長就任。1981年(昭和56年)東寺真言宗宗務総長。1992年(平成4年)解任?。(略歴は東寺真言宗#組織を参照)
- 砂原秀遍(1925-2019)<1992-2004>:自坊は観智院。東寺長者256世。
- 森泰長(-2016)<2004-2016>:自坊は宝菩提院。大分県出身。1972年入寺。2004年、東寺執事長。在職で2016年2月21日死去。67歳。
- 砂原秀輝()<2016->:砂原秀遍の長男。総務部長を経て2016年3月1日、執事長就任。
東寺大勧進
憲静以来、泉涌寺長老が東寺大勧進職を兼任したという。ただし全てではないようだ。
- 憲静(1215-1295)<1279-1294?>:泉涌寺長老6世。1279年(弘安2年)東寺大勧進職に就任。1285年(弘安8年)東寺の五重塔を再建。
- 無心覚阿(1237?-?)<1294?-?>:泉涌寺長老7世。
- 兀兀知元(?-1326?)<1306->:泉涌寺長老8世。1306年(徳治1年)東寺大勧進職。
- 全信()<1332-?>:泉涌寺長老10世。1332年(元弘2年/正慶1年)光厳天皇が東寺大勧進職。
- 文観(1278-1357)<~1334~>:弘真。1334年(建武1年)在職。1335年(建武2年)東寺長者。
- 全信()<1339-1339>:再任。1339年(延元4年/暦応2年)光厳上皇院宣で東寺大勧進職。
- 朴艾思淳1278-1363)<1339->:泉涌寺長老12世。1339年(延元4年/暦応2年)11月、東寺大勧進職。
- 天機玄勇()<1344-?>:泉涌寺長老13世。1344年(興国5年/康永3年)9月、光厳上皇院宣で東寺大勧進職。
- 月航全皎(?-1356)<1354-?>:泉涌寺長老14世。1354年(正平9年/文和3年)就任。
- 松峰知一()<>:泉涌寺長老15世。
- 明源()<>:
- 覚蔵()<>:
- 円了()<>:
- 宝栄()<~1445~>:1445年(文安2年)在職。
東寺奉行
東寺大仏師職
- 運慶
- 湛慶
- 康勝
- 康誉
- 康俊
画像
年表
- 793年(延暦12年):食封1000戸が東寺・西寺に与えられる。
- 794年(延暦13年):桓武天皇、平安京遷都。東寺の明確な創建年代は不明だが、遷都まもない時期に建てられたらしい。『東宝記』によれば東寺創建とほぼ同時期に鎮守八幡宮も創建されたと伝える。
- 795年(延暦14年):造東寺長官に大納言藤原伊勢人を任命(『東宝記』『帝王編年記』)。この頃、既に造東寺司が設置されていたらしい。
- 796年(延暦15年):一説に金堂建立(『東宝記』)。
- 806年(大同1年):空海、唐から帰国。
- 819年(弘仁10年):空海、高野山に金剛峰寺を開く。
- 823年(弘仁14年)10月10日:嵯峨天皇、空海に東寺を勅賜(『類聚三代格』)。真言宗僧50人の所属が認められた。真言宗以外の僧を認めなかった。官寺で宗派を限定するのは当時は異例だった。
- 弘仁年間:空海、八幡三所御体と武内宿禰の出現を感得し、鎮守八幡宮を重ねて勧請したという(『東宝記』)。
- 824年(天長1年):造東寺所別当に空海が任命された。
- 825年(天長2年):一説に講堂建立(『帝王編年記』)。
- 826年(天長3年):五重塔建立。
- 826年(天長3年):空海が五重塔造営のための材木を伏見稲荷大社の稲荷山の神木から調達したところ、稲荷神が祟りをなし淳和天皇が病気となったため、翌年朝廷は伏見稲荷大社に神階従五位下を贈った(『類聚国史』)。のち空海が稲荷神と出会ったという伝説が生まれる。
- 828年(天長5年):空海、東寺の東隣に綜芸種智院を開校。
- 835年(承和2年)3月21日:空海、高野山で死去。
- 836年(承和3年)5月:初めて東寺長者が設置され、実恵が任命された。ただし後世には空海が初代東寺長者とみなされた。
- 839年(承和6年)6月15日:講堂の仁明天皇御願本尊の開眼法要(『続日本後紀』)。
- 841年(承和8年):東寺二長者が初めて設けられ、真済が任命された(『東寺長者補任』では843年(承和10年)とする)。
- 843年(承和10年)11月16日:東寺で灌頂を初めて行う。この頃灌頂院建立。(『続日本後紀』)
- 872年(貞観14年):以後、東寺長者(東寺一長者)が僧綱所の「法務」を兼務
- 877年(元慶1年)頃:聖宝の導師で食堂の千手観音の開眼法要。
- 898年(昌泰1年):東寺三長者が初めて設けられ、峰教が任命された(『東寺長者補任』では894年(寛平6年)とする。)。
- 918年(延喜18年)6月24日:金堂、落雷で焼失(『扶桑略記』)。
- 969年(安和2年):東寺四長者が初めて設けられ、寛忠が任命された。
- 1000年(長保2年)11月25日:北倉、焼失(『東寺宝蔵焼亡日記』)。
- 1055年(天喜3年):五重塔、落雷で焼失(『東寺塔供養記』)。
- 1086年(応徳3年)10月20日:五重塔再建(『東寺塔供養記』)。
- 1127年(大治2年)3月9日:南倉、焼失(『百錬抄』)。
- 1167年(仁安2年):東寺長者が兼務する法務職とは別に、仁和寺門跡覚性入道親王が総法務に任命され、法務の権威は無力化した。
- 鎌倉時代初期:文覚の請願で源頼朝が復興に着手。
- 1167年(仁安2年)4月23日:伏見稲荷大社の下御旅所(七条油小路)のことが『山槐記』に記載。
- 1189年(文治5年)12月24日:後白河法皇、播磨国を修造国として寄進(『玉葉』)。
- 1191年(建久2年):備中・備後など11国が寄進される。
- 1192年(建久3年)頃:文覚の復興が本格化。
- 1198年(建久9年):東寺大仏師職に運慶が任命された。
- 1199年(正治1年):源頼朝死去で文覚が失脚。東寺復興も中断。
- 鎌倉時代初期:ついで宣陽門院(後白河天皇皇女)が帰依。後三条院勅旨田などを寄進。
- 1233年(天福1年)10月15日:空海像(仏師康勝)が造立され、西院不動堂に奉安された。
- 1240年(仁治1年)3月21日:西院不動堂の空海像が北面に置かれ、御影堂が成立。この頃、御影供が始まる。
- 1235年(嘉禎1年)11月21日:朝廷、東寺の復興事業を認め、修造料所として肥後国を寄進(『東寺長者補任』)。
- 1270年(文永7年):五重塔焼失(『東寺塔供養記』)。
- 1278年(弘安1年):五重塔再建(『東寺塔供養記』)。
- 1279年(弘安2年):亮禅、宝菩提院を創建。
- 1282年(弘安5年):東寺絵師職に快智を任命(『阿刀文書』)。この頃には東寺絵所が成立していたらしい。
- 1293年(永仁1年):五重塔再建
- 1306年(徳治1年):禅助、東寺灌頂院で後宇多法皇に灌頂を授ける(『東宝記』)。この頃、後宇多法皇の御願寺として観智院を創建。
- 1317年(文保1年)1月3日:地震で五重塔の九輪が破損(『東寺塔供養記』)。
- 1326年(嘉暦1年):後醍醐天皇、東寺講堂で『仁王般若経』講説。最勝光院執務職を東寺に寄進。
- 1330年(元徳2年):後醍醐天皇、宝荘厳院執務職を東寺に寄進。
- 鎌倉時代末:東寺光明真言講が始まる。
- 1333年(元弘3年/正慶2年)6月4日:隠岐より帰還した後醍醐天皇が入京し、まず東寺に滞在(『公卿補任』)。
- 1334年(建武1年)9月24日:後醍醐天皇が行幸して五重塔再建法要(『東寺塔供養記』)。
- 1336年(延元1年/建武3年)6月14日:足利尊氏が光厳上皇らを奉じて入京し、東寺に滞在。東寺を上皇御所とした(現在の小子房)。灌頂会断絶。(『皇年代略記』)
- 1353年(正平8年/文和2年)6月:南北朝の戦いで将軍足利義詮が陣とした。盗賊が東寺に入り被害。(『園太暦』)
- 1379年(天授5年/康暦1年)12月4日:御影堂・小子房、焼失(『東宝記』)。
- 1380年(天授6年/康暦2年):御影堂を再建。
- 1486年(文明18年)9月13日:文明の土一揆で金堂・講堂・南大門など焼失(『東寺百合文書』など)。
- 1491年(延徳3年):講堂再建。
- 1563年(永禄6年):五重塔、雷火で焼失(『御湯殿上日記』)。
- 1568年(永禄11年)9月:入京した織田信長が東寺を宿所とした(『言継卿記』)。
- 1585年(天正13年)11月29日:地震で金堂倒壊。灌頂院大破。(『宇野主水日記』)
- 1591年(天正19年)9月:豊臣秀吉、2030石を安堵。
- 天正年間:豊臣秀吉、伏見稲荷大社の上御旅所と下御旅所を合併し、現在地に移したという。
- 1594年(文禄3年):五重塔再建(『御湯殿上日記』)。
- 1596年(慶長1年)閏7月13日:大地震。諸堂被害。講堂大破。(『義演准后日記』)
- 1598年(慶長3年):北政所、講堂修復。
- 1601年(慶長6年):南大門再建。
- 1603年(慶長8年)5月:豊臣秀頼、金堂復興。(1606年(慶長11年)?)
- 1605年(慶長10年):観智院客殿再建。
- 1609年(慶長14年):幕府の命で観智院を勧学院と定める。
- 慶長?:徳川幕府、東寺に「真言宗法度」を発布。
- 1634年(寛永11年):灌頂院再建。(1633年(寛永10年)とも)
- 1644年(正保1年):徳川家光の寄進で五重塔再建。
- 1685年(貞享2年):金沢藩主前田綱紀が『東寺百合文書』を整理書写し、保管のための書櫃100箱を寄進した。文書名はこの箱の数に由来する。
- 1834年(天保5年):空海1000年忌。
- 1868年(明治1年)10月:南大門・八幡宮・八島社、焼失。
- 1872年(明治5年)10月3日:政府は真言宗管長を設置。「単称真言宗_(第1次)」が成立し、東寺も所属する。
- 1883年(明治16年)1月8日:明治初年に廃絶した後七日御修法が東寺灌頂院を道場として復興した。
- 1895年(明治28年):蓮華王院西門を南大門として移築。
- 1900年(明治33年)8月10日:真言宗内で、統一教団を支持するグループ(画一派)と、分派を求めるグループ(分離派)の対立が決定的となり、7派が単称真言宗から独立し、統一教団が崩壊(内務省告示第74号)。東寺は「単称真言宗(第1次)」に残留。
- 1901年(明治34年)7月5日:「単称真言宗(第1次)」も、独立宗派が作った「真言宗各派連合」に加盟。
- 1907年(明治40年)12月7日:「単称真言宗(第1次)」が消滅。東寺は真言宗東寺派を創設。真言宗東寺派も引き続き「真言宗各派連合」に加盟。(内務省告示第126号)
- 1922年(大正11年):東寺勅賜1100年記念大法会。
- 1925年(大正14年)9月24日:真言宗各派連合廃止を文部省認可。(官報)
- 1930年(昭和5年)12月21日:食堂焼失。「終い弘法」の縁日の日だった。
- 1933年(昭和8年):食堂再建。
- 1934年(昭和9年):空海1100年忌。
- 1934年(昭和9年):小子房を再建。
- 1940年(昭和15年):金堂解体修理。
- 1941年(昭和16年)3月31日:真言宗東寺派、「単称真言宗_(第2次)」に合併(文部省告示第503号)。
- 1946年(昭和21年):「単称真言宗_(第2次)」から離脱し、再び真言宗東寺派を組織し、宗教法人設立(『仏教宗派辞典』)。
- 1952年(昭和27年):真言宗東寺派、宗教法人認証登記(『仏教宗派辞典』)。
- 1954年(昭和29年):講堂解体修理。
- 1965年(昭和40年):宝物館開館。
- 1967年(昭和42年):東寺、『東寺百合文書』を京都府に譲渡。
- 1974年(昭和49年):東寺と宗派が対立。東寺が真言宗東寺派を離脱して東寺真言宗を新たに設立した。
- 1984年(昭和59年):空海1050年忌。
- 1992年(平成4年):鎮守八幡宮、再建。
- 1994年(平成6年):「古都京都の文化財」の構成資産として世界遺産登録。
- 1995年(平成7年):東寺創建1200年記念法会。
- 2000年(平成12年):大日堂再建。
- 2015年(平成27年):『東寺百合文書』が世界記憶遺産に登録。
- 2019年(平成31年):御影堂、修復竣工予定。